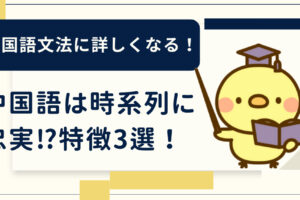こんにちは、Shuです。
前回これでもう迷わない!中国語はじめの知識で、中国語はSVOが基本、という話を書きましたが、
今回は、
SVOだけじゃないぞ、中国語の語順には8つも例外パターンがあるんだぞ、という話を紹介します。
これをはじめに知っていると、
その後の新出例文に触れたときに
「え!なんで!?どういうこと!?」
とあたふたしなくて済むのでぜひ頭に入れておいてもらえると
「太好了」(よかった〜)ですよ🎵
では、いってみましょうーー!
Contents
①前置目的語
こちらは、目的語が前に来るパターンです。
中国語では、SVOではなくOSVになることが多々あります。
文:這本書我看過了。
形:OSV
英語の意味は、
I have read this book. (私はこの本読んだことがあります。)
↓
This book I have read.(この本私は読んだことあります。)
(V= have read)
筆者はてっきり、「あ!この本!!わたし読んだことある!」の強調ニュアンスなのかと思って主人に聞いてみたら、そういうわけではないらしい。
「んーまぁ、この本は読んだことがあります、って感じかな。」だと。驚
台湾人てきには逆に、
我看過了這本書。(人が文頭にくる)
のほうがちょっと違和感があるみたいです。
②S被構文(受け身文)
こちらは受け身文(〜された)を作るときの形です。
受身文をつくるときは、
受けた人やモノ+被+加害者(行為者)+動作の順で言葉を並べます。
文:他被老師批評了。
形:S被OV
例文1:他被老師批評了。(彼は先生に叱られた。)
他 → He
被 → 受け身のis ~ed
老師 → 先生
批評了→ 叱った
例文2:手機被他弄壞了。(スマホが彼に壊された)
手機 → スマホ
被 → 受け身のis ~ed
他 → he
弄壞了→ 壊した
行為者不明の時は、加害者(行為者)の部分を丸ごと省略してOK!
・お金盗まれた!我的錢被偷了。
・ドアを閉められた!門被關了。
解説:
我的錢→ 受けた物
被 → 受け身のis ~ed
偷了 → 盗んだ
門 → ドア
被 → 受け身のis ~ed
關了 → 閉まった
③ちゃんとやった!把構文
つづいて、処置完了を伝える把構文。
ちゃんとやった!感を強調するとき以下のようにいいます。
文:我把作業寫完了。
形:S把OV
「何かをどうにかしたよ」
「やるべきことをやったよ」
「すっきり完了したよ!」
ということを伝えるときに「把」を使います。
例えば…
・ちゃんと机の上に置いた!我把書放在桌上!
・ちゃんとドア閉めたよ!我把門關上了!
・宿題終わらせたよ!我把作業寫完了!
「〜を〜する」という単調な言い方ではなく、
「〜をどうしたか」をより明確にしたいときに使うんだ、と覚えておけばOK!
④連動文
中国語では、「AしてからBする」のような文を作るときに連続する2つの動詞の順番が変わることがあります。
例えば、
日本語では「買いにいく」といいますが、
中国語では「行って、買う」=去買の順番になる。(中国語は時系列に忠実)
文:我去買東西。
形:SV+VO
おでんを買いに行く。→去買關東煮🍢。
買去ではなく、
去買の順番です。
「先にする行動(移動)」+「その目的」
です。順番に要注意ですよー!
ちなみに、友達の家にいくときの
「寒いよね〜!おでん買っていくね〜」の「買っていくね」と言いたいときは
我要去買關東煮。になります。
「いま家出たよ(我現在出門了。)
おでん買っていくね、(我要去買關東煮。)
待ってて〜!(待著喔!)」
という感じで言います。
⑤補語構文
動作の状態や内容を表すときには補語構文を使います。
文:他跑得很快。
形:SV補語 or SV補語O
注釈:補語とは…動詞の後について、動作の内容や状態をもっと詳しく説明する言葉です。
SVO…私はごはんを食べた。
SV補語…私はご飯を食べてお腹いっぱいになった。
補語と一口に言っても、いろんな役割があります。
例えば【程度補語】は、
強い⇔弱い、深い⇔浅い、速い⇔遅い、広い⇔狭いなどを表します。
| 日本語 | 中国語 | 形 |
| 彼はとても速く走る | 他跑得很快 | SV補語 |
他にも以下のような補語構文があります。
| 補語の種類 | 日本語 | 中国語 | 形 |
| 形容詞的補語 | 美味しく食べる
ぐっすり眠る |
我吃得很美味
他睡得很香 |
SV補語
SV補語 |
| 結果補語 | お腹いっぱいになった
宿題をやり終えた |
我吃飽了
我做完作業了 |
SV補語
SV補語O |
| 方向補語 | 教室に入った
家に帰った |
他走進了教室
他走回家 |
SV補語O
SV補語 |
形の表を見ると、SV補語Oのものもありますが、基本的に補語の位置がSVの後であることに変わりはありません。
⑥是的構文
過去の出来事や情報を強調するときに「是~的」を使います。
文:她是坐飛機來的。
形:S是(強調したい部分)V的
例えば…
飛行機で来たの?你是坐飛機來的嗎?
うん、飛行機で来た。對、 我是坐飛機來的!
↑「飛行機で!!」と強調してるってこと。
田舎のおばあちゃんとかに会いに行って、
「あんた、飛行機で来たん?」
「うん飛行機で!」
という会話に使えそうなニュアンスですね。w
◆他の例文:
♥ 我是昨天來的。(私は昨日来た。)←昨日を強調
♥ 我們是在台北認識的。(私たちは台北で知り合った。)←台北でを強調
「是的構文」のポイントは、
- 「いつ」「どこで」「どうやって」などを強調したいときに使う
- 過去の出来事の説明に使われる
- S是(強調したい部分)V的←このように間に強調したい部分を入れる。
ということ!
ただし、強調しなくても全然OK。もし強調しない場合は、
♥ 我昨天來。(私は昨日来た。)
♥ 我們在台北認識。(私たちは台北で知り合った。)
のように、是と的を抜いて言えば大丈夫です。
⑦存在表現(ある/いる構文)
つづいて、「机の上」が主語になるパターン。
あるいる構文では場所を先に持ってくるのが自然。
文:桌上有一本書。
形:基本のSVOだが主語の転換が起きる
例えば、「机の上に本が一冊ある。」という文があるとしましょう。
桌上有一本書。
ここでは、「机の上」という場所を「主語」にしっちゃってます。
「場所を主語に!?」と思うでしょうが、中国語はこれが普通です。
これでもう迷わない!中国語はじめの知識でも少し触れましたが、
中国語では、話題となる人や物を文頭に持ってくることがよくあります。(トピック優先構文)
Japanese food, Taiwanese people love sushi.
(日本食、台湾の人はお寿司がすきです。)
→ここでも、Japanese food(日本食)が主語に来ています。
中国語だと、
日本料理,台灣人喜歡壽司。
(Rìběn liàolǐ, Táiwān rén xǐhuān shòusī.)
日本料理でいうと、台湾人は寿司が好きです。
みたいな感じ。
中国語ではまさにこういう構文が自然。「話題(日本料理)」を先に出すのが中国語らしいんですね。
だからこそ、「机の上有一本書」みたいな構文も中国語ではごく自然!
中国語は、なんの話してるのか、はっきりさせたい言語なのか??笑
日本語や英語との大きな違いが垣間見えて面白いですねぇ!
⑧【補足】ある不特定多数のもの(人)については主語省略
中国語は存在と現象に関わる事象を表すとき、独特な構造をとります。
ある不特定多数のもの(人)については主語省略
文:有一個大聲音。
形:VO
theがつく(その〇〇のような)存在や、
予測できたものや、特定されたもの(人)の場合…
例えば、「この雨は止んだ」の「この雨」など特定されたものについて言いたいときは、主語は「這場雨」であり、通常通り動詞の前にきます(文:這場雨停了。)
一方で、
予測できなかったことや、不特定多数のもの(人)の場合…
例:有一個大聲音(大きな音がした)の「大きな音」が主語であり、ある一つのある音と言うふうに表現して、動詞の後に置かれます。
まとめ
ここまでの例外パターン8選を以下にまとめます。
①目的語が前に来る文
這本書我看過了。
OSV
→目的語が前に来るパターン
②S被構文
他被老師批評了。
S被OV
→受けた人やモノ+被+加害者(行為)+動作で受け身表現になる。
③ちゃんとやった!構文
我把作業寫完了。
S把OV
→ちゃんとやった!を強調し処置完了を伝える。
④連動文
我去買東西。
SV+VO
→「買いにいく」という日本語てきな言い回しが、中国語では「行って、買う」=去買の順番になる。これを連動文という。
⑤補語構文
他跑得很快。
SV補語またはSV補語O
→動作の状態や内容を表すときに使う。
⑥是的構文
她是坐飛機來的。
S是(強調したい部分)V的
→いつ、どこで、どうやってなどを強調するときに使う。
過去のことを説明するときに使う。
⑦ある/いる構文
桌上有一本書。
基本のSVOだが主語の転換が起きる
机の上が主語になるパターン。
→あるいる構文では場所を先に持ってくるのが自然。
⑧【補足】ある不特定多数のもの(人)については主語省略
有一個大聲音。
VO
→theがつく予測できたものや、特定されたもの(人)の場合、主語は前の前方動詞の前に来るが、予測できなかったことや、不特定多数のもの(人)については、主語が動詞の後に来ることがある。
難しかったですか?
こちらの記事はより初心者向けです🔰
中国語文法に詳しくなる!特徴3選!